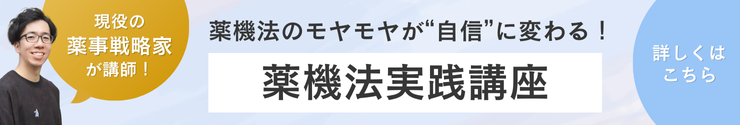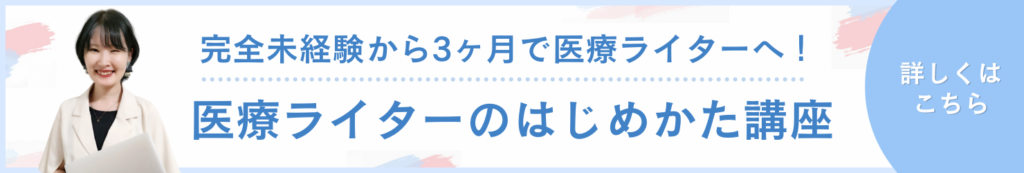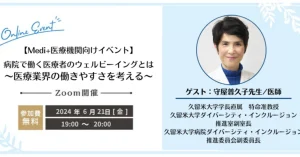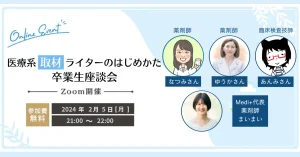薬機法、景品表示法、健康増進法、医療広告ガイドライン――。医療系クリエイターが仕事をするうえで避けては通れない壁です。
「いろんな法律があって、どれにあてはまるのかわからない」
「専門的な言い回しで、独学だと解釈が難しい」
「意識しすぎて、無難な表現以外使えていない……」
そんな悩みを持つWebクリエイターのために、医療者専用リスキリングスクール・Medi+(メディタス)は、2024年5月に「第1回薬機法実践力向上講座」をリリース。好評につき、2024年9月から第2回を開催しています。
今回は本講座の講師である、玉井智大さんにお話を伺いしました。
この記事では、現在10社以上の薬事戦略責任者としてコンサルティング業や講師業に携わる玉井さんに、「薬事戦略責任者」の仕事について、そしてMedi+「薬機法実践力向上講座」の魅力とこだわりについて教えていただきました。

Medi+「薬機法実践力向上講座」講師/薬事戦略家
玉井智大
薬学部卒業後、製薬会社の臨床開発職に6年半従事。コロナ禍をきっかけに製薬会社を退職し、薬機法ライターとして2020年に独立。現在は多くの企業の薬事戦略責任者として活躍。「Medi+薬機法実践力向上講座」講師。
薬事戦略家として活躍中!講師・玉井智大さん
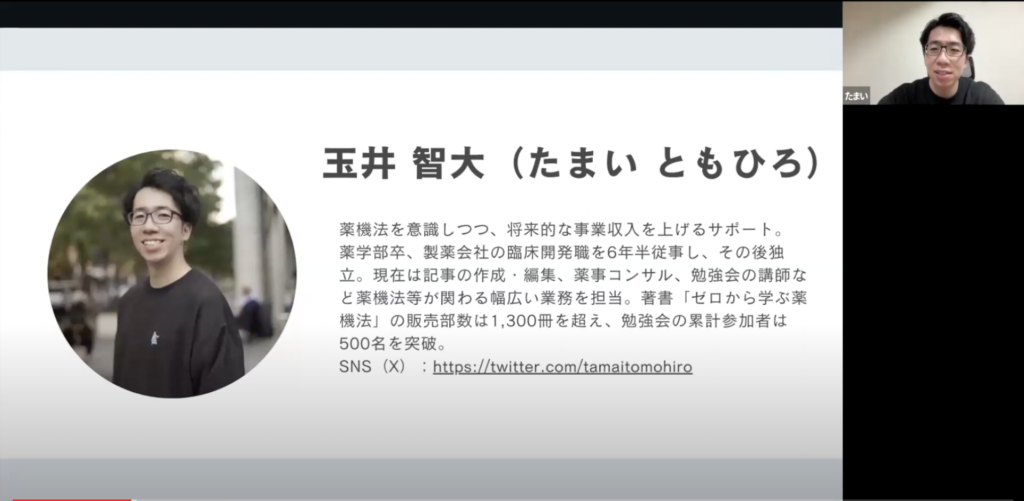
松岡磨衣子(以下、まいまい):
本日はよろしくお願いします。さっそくですが、玉井さんが薬事戦略家として、薬機法に特化することになったきっかけを教えてください。
玉井智大(以下、玉井):
最初は、セレクトショップを経営している知人に「化粧品や健康食品のポップ広告*を作ってほしい」と依頼されました。ポップ広告を作るにあたって、キャッチコピーなど薬機法を遵守しなければなりません。
薬学部を卒業しているので、大学のカリキュラムとして学ぶべき「薬機法」は知っていました。そのため、薬機法を遵守して広告が作れるだろうと安請け合いしてしまったのがきっかけです。
当時は、薬機法の知識としては国家試験対策で少し勉強した程度でしたが、案件を行う中で「広告として使用する薬機法は、薬学部で学ぶ薬機法とは内容が大きく異なる」ことを知りました。仕事で使うほどのスキルもなく、安請け合いしたことを後悔しましたね。
しかし、仕事として受けるのであれば、「広告として使用する上での薬機法」をしっかりと勉強しようと一念発起。これが薬機法ライターの仕事のスタートです。
まいまい:
現在、玉井さんは「薬事戦略家」として活動されていますが、どのような経緯で薬機法ライターから薬事戦略家に変わったのですか。
玉井:
私は最初は薬機法ライターとして活動していました。当時感じていたのが「薬機法を意識して言い換え表現すると、自分の使いたい表現が使えない」ということです。
限られたルールの中でしか表現できないことを、とてももどかしく感じていました。薬機法に携わっている医療ライターさんなら誰しも感じたことがあるのではないでしょうか。
しかし、この「使いたい表現が使えない」という問題が、そもそものコンセプトやターゲットなど、根本を見直すことで解決できる場合があるんです。あるクライアントに「ホームページの構築内容をこう変えたら、言いたいことをすべて表現できます」など提案するようになったのが、薬事戦略家となったきっかけです。
少しずつ、企業の中に入って商品構成やLP*構築などから関わって仕事をするようになったため、薬事戦略家と名乗るようになりました。
現在は企業の薬機法・景品表示法のマニュアル作りなどにも携わっています。とくに上場を目指す企業になると、法律の遵守はより厳格になるので、攻めた表現もしづらくなるんです。
そのような厳格な法律に則ったうえで、最大限に商品やサービスの魅力を伝えられる表現を使ったサイト構築を心がけています。
医療系クリエイターが薬機法を学ぶべき理由

まいまい:
業界を熟知している玉井さんから見て、医療系のクリエイターが薬機法を学ぶべき理由は何だと思いますか。
玉井:
医療系のクリエイターの仕事は、化粧品・健康食品・医療機器・医療機関の宣伝など、医療系だからこそできる専門性の高い仕事が多くあると思います。これらには必ず薬機法が関わってきます。
少しネガティブな言い方になりますが、学ばないとみずから仕事の幅を狭めてしまう。
「自分の仕事の幅を広げたい」「自分のやりたい仕事をしたい」と考える医療系クリエイターであれば、薬機法を学ぶべきだと思います。
実体験を詰め込んだ「薬機法実践力向上講座」
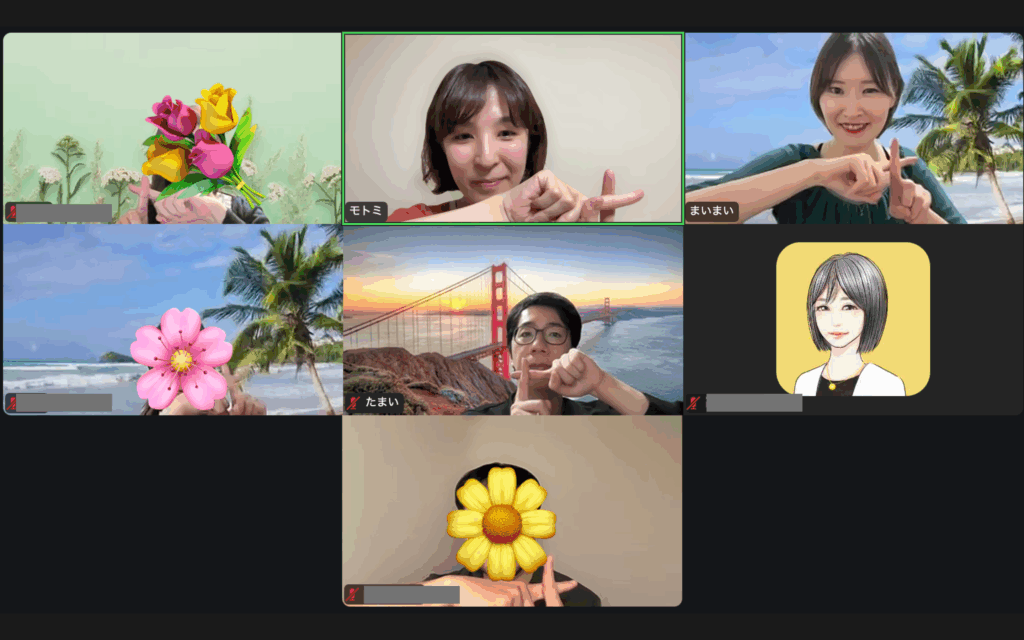
まいまい:
玉井さんには実際に経験したクライアントワークをもとにして、Medi+の「薬機法実践力向上講座」の構築から講師・課題作成・質問対応まで携わってもらっています。玉井さんが考える、本講座の魅力や講座を作るうえで重視したところを教えてください。
玉井:
私が講座を作るうえで一番意識しているのは、効率的かつ実践的に薬機法を学べることです。
薬機法は厚生労働省などによりWebでも公開されているので、正直誰でも無料で読めます。しかし自分ですべての内容を読み、理解して実践するのはとても大変です。本講座では薬機法をわかりやすく、なおかつ実践に活かせるかを重視して作り上げています。
膨大な量の薬機法のガイドラインの中から、優先的に知っておくべきことを可能な限り厳選し、効率的に学べるように構築しています。
まいまい:
Medi+では4年ほど前から「医療ライターのはじめかた」講座を運営しています。そのなかにも薬機法や景品表示法、健康増進法を学ぶ初心者医療ライター向けのプログラムがあるのですが、卒業生から「インプットできる場所はたくさんあるが、アウトプット力を学ぶ場所がなく、卒業した後実際に仕事をするときに不安が残る」という悩みをよく聞きます。
「薬機法実践力向上講座」はそんな方のために構築した経緯があるのですが、講座での具体的な工夫を教えてください。
玉井:
通常の学習過程として、インプットをしてからアウトプットをして学んでいくと思います。しかし、薬機法に関しては学ぶべき知識量が膨大すぎて、インプットの時点で諦めてしまうのです。
「医療ライターのはじめかた」講座と違うのは、やはりカリキュラムのすべてが「医療系を中心とした広告に対する、実践的な法律知識とスキルを学ぶ」となっているところですね。薬機法実践力向上講座では、一定量のインプットをしたらすぐに課題でアウトプットするという流れにしています。
そのため、挫折をせずに学べる、学びやすさを意識しています。
当講座の課題は、私がこの6年間で受けた実際のクライアントワークをほぼそのまま使用しています。課題に取り組むなかで、受講生はクライアントへのベストな提案をするスキルも会得できるようになります。実際に私が受注した案件に取り組むので、実践力が身につくと思います。
まいまい:
私も課題を拝見しましたが「こんな案件があるんだ」「こういう形で依頼されるんだ」という発見があり、課題を通して実際のクライアントワークの疑似体験ができると感じました。
玉井:
薬機法実践力向上講座の課題については、初めて薬機法を学ぶ人にとってレベルが高いものかもしれません。
しかし、この課題をクリアできれば、実際の現場でのクライアントワークのハードルは下がると思います。
まいまい:
講座受講中は、テキストでの相談や質問は無制限です。講座受講中最低1回は玉井さんを含めた運営と講座受講生の交流会も設けています。
テキストで言語化しにくい質問なども、玉井さんと顔を合わせて質問できる機会を作っているので、受講生さんにぜひ活用していただきたいポイントです!
薬機法を学びたい医療系クリエイターへひとこと

まいまい:
最後に玉井さんから薬機法を学んでいきたいと思っている医療ライターや医療系デザイナー、SNS運用者などの方々にエールをお願いいたします!
玉井:
私が薬機法に関わる仕事で大切にしているのは「薬機法に則った表現は、必ずしも100%の白黒を付けるわけではない」ということです。実際に世の中に出ている広告やクライアントワークで、ガイドラインや法律上、使えないとされている表現が使われていることがあります。
「NGとされている表現が、実社会では使われている」ことが、薬機法を学ぼうとする方や受講生が混乱してしまう部分ではないでしょうか。
たとえば、化粧品で持続時間の保証は記載することができないのに「保湿が丸1日続きます」「24時間保湿のデータがあります」と表現されていることがあります。では、なぜこのような記載ができるのでしょう。
そんな薬機法やガイドラインを文面で読んでいるだけでは矛盾が生じてしまう部分を実際の現場の経験を活かして解説しています。
薬機法を学べる手段は多くありますが、薬機法に特化して長年仕事している人は少ないでしょう。私が6年間にわたり、薬機法に携わった経験を詰め込んでいる本講座では、金額・労力・時間を総合的に考えて効率的に学べると思います。
これから薬機法を学んでいきたい方、自分一人で解決できない方はぜひ一度相談していただければと思います。
薬機法実践力向上講座 医療・美容・健康系のライター/デザイナー/SNS運用者に向けて、薬機法/景表法/健康増進法/医療広告ガイドラインなどを意識した「言い換え表現」を実践的に学ぶ講座です。知識があっても、実践が不安な方におすすめです!