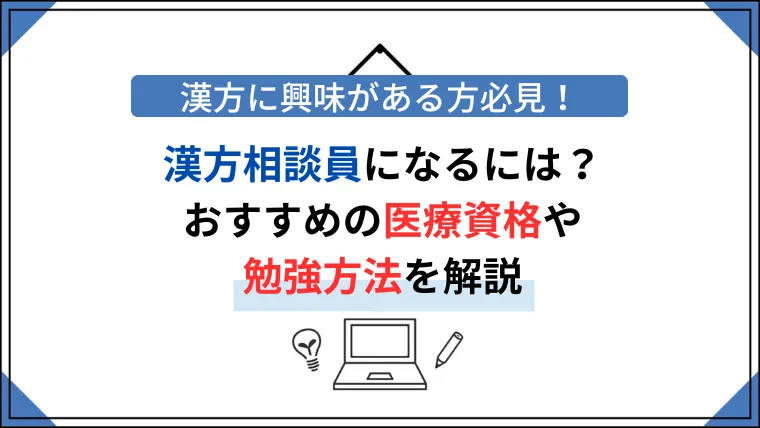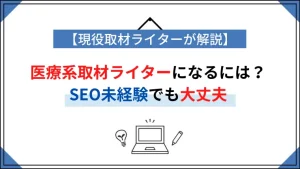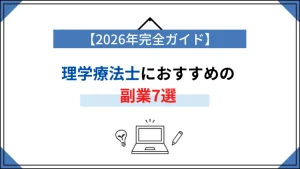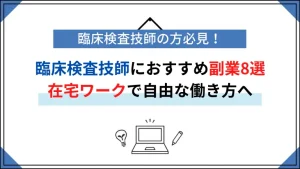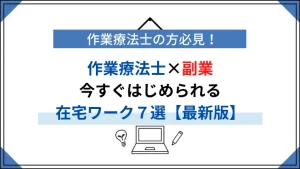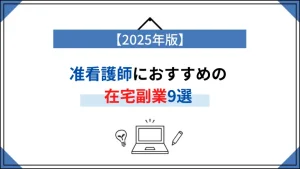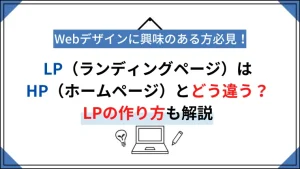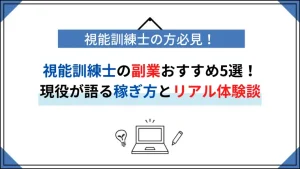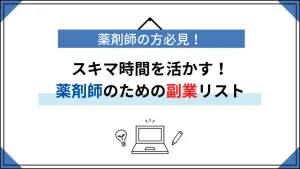「漢方について専門的な知識を学び、自信をもって患者さんへアドバイスをしたい」
「漢方の基礎や薬膳などを学び、日常に取り入れることで患者さんの健康を総合的にサポートしたい」
医療資格保有者として経験を積んできたけど、漢方の相談を受けた際に不安を感じることはありませんか?漢方は種類が多いうえに、患者さんの体質や生活習慣によって処方がさまざまで複雑ですよね。
漢方の服薬指導に不安を感じている人に、漢方相談員という働き方があるのはご存じでしょうか。漢方相談員は、患者さんとしっかりコミュニケーションをとり、一人ひとりに合ったアドバイスする漢方の専門家です。
 薬剤師ライター
薬剤師ライター三木あこさん
本記事では漢方相談員になるためのおすすめの資格や勉強法について、薬剤師ライターである筆者が解説します。
漢方相談に対応する不安が解消されるようまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
漢方相談員とは


漢方相談員とは、漢方について専門的な知識を持つ、漢方のプロフェッショナルです。漢方の知識を用いて患者さんに服薬のアドバイスをします。
日本で漢方を含め医薬品を販売するためには、薬剤師または登録販売者の資格が必要です。しかし漢方相談員は、資格がなくても専門的な知識があれば、漢方の選び方や日常への漢方の取り入れ方をアドバイスできます。
漢方は医療現場で広く使われており、身近なものとなっています。



三木あこさん
薬剤師、登録販売者、管理栄養士、看護師など、相性の良い医療資格はさまざまです。
漢方を適切に使うために、漢方相談員という働き方は今後も需要が高まるでしょう。
漢方相談員の仕事内容
漢方相談員の仕事は、主に2つあります。
- 患者さんのカウンセリング
- 漢方の使い方や生活習慣についてアドバイスする
漢方は体質や生活習慣によって使い方が変わってくるため、患者さんのカウンセリングをじっくりおこなうことがとても大切です。[1]
カウンセリングでは、顔色や体の動きなどの全身の状態、症状の経過、疲れやすいかや汗っかきかなどの体質について、くわしく確認します。



三木あこさん
実際に、筆者が漢方薬局で実務実習をおこなった際、漢方相談員は1時間ほどかけてカウンセリングしていました。
漢方相談員が活躍する場
漢方を取り扱うすべての場で、専門知識をもつ漢方相談員の活躍が期待されます。
調剤薬局や漢方薬局、病院、クリニックなどの臨床現場はもちろんですが、セルフメディケーションの普及に伴い、近年ではドラッグストアでの漢方相談も増えています。
また、漢方相談員としての知識は、ドラッグストアで働く登録販売者、薬膳レシピや薬膳コーディネーターを行う管理栄養士、漢方専門外来で働く看護師など、さまざまな医療資格保有者が多くの場所で活用できます。
製薬会社においても、漢方の専門的な知識はキャリアアップにつながるでしょう。



三木あこさん
オンライン漢方相談では在宅ワークが可能なので、子育て中の方や副業にもおすすめです。
漢方相談員におすすめの資格5選
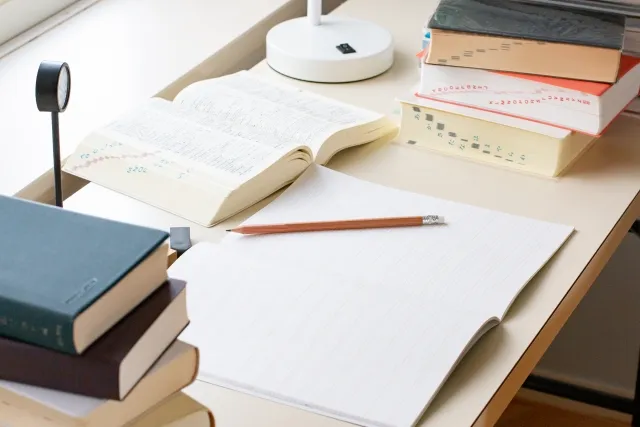
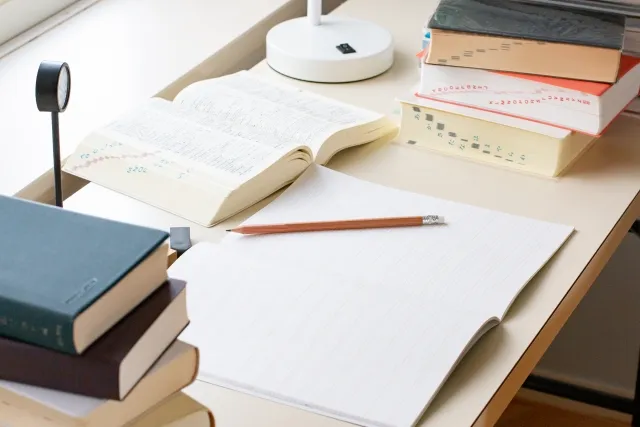
漢方相談員になるために必須の資格がない一方、漢方の専門的な知識は必要不可欠です。
漢方に関する資格は、日常で使える基礎知識から仕事にも活かせる専門知識、さらには薬剤師のみが取得できるものまでたくさんあります。
本章では、医療資格保有者が漢方相談員として活躍するために、おすすめの資格を4つ紹介します。
国際中医師
国際中医師とは、中国の伝統医学である中医学の知識をもつ専門家です。中国では西洋医師とは別に、中医学を専門とした国家資格である中医師が存在します。
国際中医師は、中医師と同じレベルの知識をもつと認められた国際的な資格です。中国政府の外郭(がいかく)団体である世界中医薬学会連合会が認定しています。いくつかのスクールが講座を開催しており、受講後に試験に合格すると資格を取得できます。[3]



三木あこさん
ただし、日本では国家資格ではないので、医療行為はおこなえません。
医療資格保有者が国際中医師の資格を取得することで、西洋医学と中医学の両方の観点から患者さんへアドバイスができるでしょう。
漢方養生指導士
漢方養生指導士は、日本漢方養生学協会が認定する資格です。コースは日常で役立つ漢方の基礎を学べるベーシックコース、漢方の性質を深く学び臨床でも活かせる薬物学マスターコースなど全部で6種類あり、目的にあわせてステップアップしながら学べます。[4]
協会の認定校である薬日本堂漢方スクールの講座を受講し、試験に合格すると資格を取得できます。また、コースによっては、通学のみの講座があるため注意が必要です。



三木あこさん
上級のコースまで取得すると、薬剤師としてのレベルアップにもつながります。
薬膳コーディネーター
薬膳とは、体質や季節にあわせた食材を組み合わせ、心と体の健康を維持する料理のことをいいます。[5]
薬膳コーディネーターは本草薬膳学院という教育機関が認定する資格です。認定機関と提携しているユーキャン通信講座を受講し、試験に合格すると取得できます。
薬膳の知識があれば食事のアドバイスができ、患者さんの日常生活により近いところで健康へのサポートが可能です。
漢方アドバイザー
漢方アドバイザーは、一般社団法人日本技能開発協会が認定をしており、漢方の基礎知識や服用方法など、幅広い知識を身につけられます。[6]
専用のテキストや問題集で学習し、自宅での受験が可能です。試験実施後、解答用紙を郵送すると、試験結果がメールで届きます。



三木あこさん
薬剤師だけでなく、一般の方も受験できるため、気軽に取得できる資格であるといえるでしょう。
漢方薬・生薬認定薬剤師
漢方薬・製薬認定薬剤師とは、漢方薬や生薬に関する専門的知識を修得し、能力と適性を備えたと認定された薬剤師です。漢方に関するさまざまな資格のなかで、薬剤師のみが取得できる資格です。[7]
資格の取得には、日本薬剤師研修センターと日本生薬学会が実施する研修を受け、試験に合格する必要があります。研修は9回の講義と1回の薬用植物園実習*があり、講義はインターネット上で受講ができます。また、定期的に研修を受け、3年ごとに更新が必要です。
合格通知が届いたら、薬剤師研修・認定電子システム(PECS)から認定申請ができます。



三木あこさん
漢方薬・製薬認定薬剤師に認定されれば、患者さんに自信をもって服薬指導ができ、医師への的確な情報提供にもつながるでしょう。
また、薬剤師の資格を持っている場合は、症状に合わせて調薬しオーダーメイドの煎じ薬を調剤することが可能です。
医療資格保有者が、漢方相談の自信をつけるには


漢方は症状だけではなく、体質や生活習慣によっても選び方や使い方が違ってくるもの。ひとりひとりへの詳しいカウンセリングがとても大切です。
しかし、漢方のたくさんの知識と、患者さんへのヒアリングスキルを独学で学ぶのは、容易ではありません。
本章では、漢方相談に必要な知識とスキルの学び方について3つ紹介します。
中医学の大学へ通う
漢方について基礎から応用までしっかりと学びたい方には、中医学を学べる大学へ入学する方法もおすすめです。講義や実習のカリキュラムが充実しており、時間をかけて本格的に学べます。
ただし、大学卒業までには数年かかり、多額の学費も必要です。



三木あこさん
薬剤師として働きながらの通学は負担が大きく、あまり現実的ではないかもしれません。
漢方薬局で実務経験を積む
薬剤師の場合、実際に漢方薬局で働き患者さんとコミュニケーションをとることで、実務を通して漢方知識とヒアリングスキルを同時に学べます。



三木あこさん
まさに、「習うより慣れよ」です。
働きながら実践で学べることは大きなメリットです。デメリットとしては、未経験者の募集が少なく、採用は難しいことが考えられます。
民間団体が主催する講座を受ける
漢方に関する講座はたくさんあるので、講座内容や受講スタイルなど、自分にあったものを選べます。オンラインやテキストをつかって自宅で学習できる講座が多いので、仕事を続けながらでも安心です。
しかし講座によっては、知識をインプットするだけで、アウトプットする機会が少ないものもあります。



三木あこさん
また、質問に回数制限が設けられている場合があるので、講座を選ぶ際は注意しましょう。
Medi+「オンライン漢方相談講座」を受講する
医療者専用リスキリングスクール「Medi+(メディタス)」では、「オンライン漢方相談講座」を開催しています。
漢方薬局を経営し、年間2500人以上の漢方相談に乗る講師が、オンライン漢方相談の基礎知識や学び方、症例検討による考え方のアプローチなどをお伝えしています。



三木あこさん
とくに、受講生2人1組で行うロールプレイングでは実際のオンライン漢方相談を想定して行われます。
講師によるデモ動画共有や個別フィードバックから学び、卒業後の働き方をイメージしていきます。
漢方の知識を活かして新しい働き方をみつけよう


漢方相談員になるために、おすすめの資格と勉強法を紹介しました。
漢方の専門知識とヒアリングスキルの両方が必要不可欠ですが、ひとりで勉強するのは大変です。
とくに、ヒアリングスキルは一朝一夕では身につかないもの。ロールプレイングや質問の機会がたくさんあり、アウトプットの場が多い講座を選ぶことがおすすめです。
漢方相談員になると服薬指導の自信がつくだけではなく、オンライン漢方相談といった在宅ワークも選べます。



三木あこさん
医療者としてのステップアップを目指し、漢方知識を活かした新しい働き方をみつけましょう。
オンライン漢方相談のはじめかた講座
漢方の歴史・現状、営業形態やオンライン店舗見学、勉強方法、ロールプレイングまで実践的に習得できる講座です。医療現場での専門知識や経験と漢方知識を掛け合わせて働きたい方に特におすすめです!