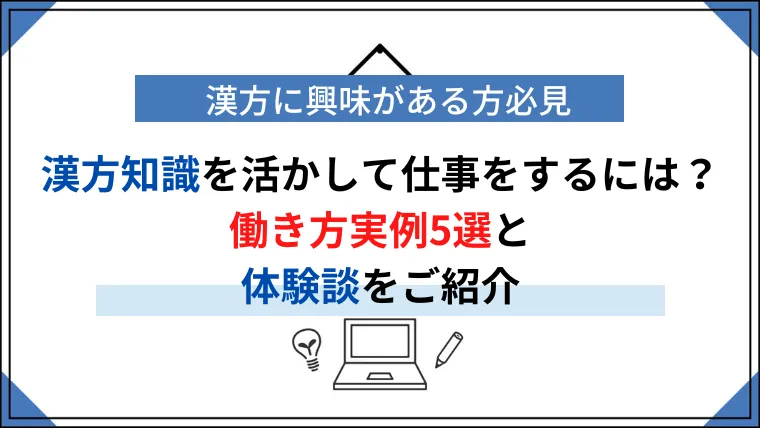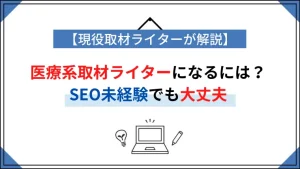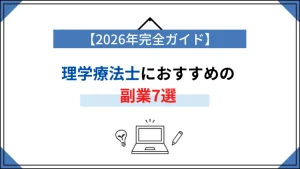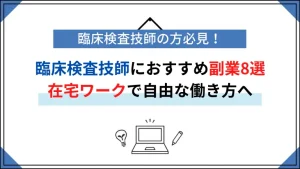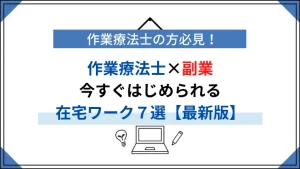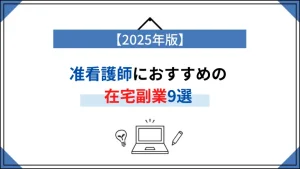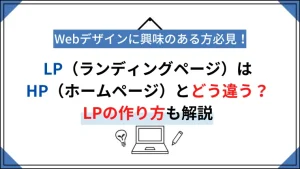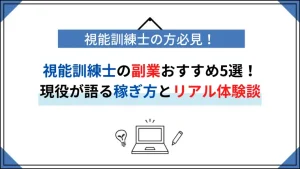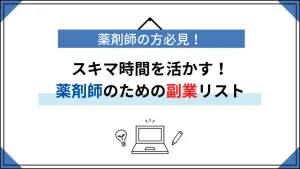「漢方に関わる仕事をしたいけど、どのような働き方があるのだろう?」
「漢方の仕事って、漢方薬局や漢方クリニック以外にもあるのかな」
実は漢方の知識は、さまざまな医療資格と組み合わせて活かせるだけでなく、副業や在宅ワークとしても活用できます。
 薬剤師ライター
薬剤師ライター山川裕子さん
漢方薬剤師である筆者も、かつては子育てをしながら在宅でオンライン漢方相談をしていました。
この記事では、漢方の知識と医療資格を活かしたユニークな働き方の実例5選と、実際に漢方の知識を仕事に活かし活躍している2人の体験談をご紹介します。
さらに、漢方を仕事にするメリットや方法についてもまとめました。
働き方について今迷っている方や、漢方に少しでも興味がある方は必見です。
漢方を活かした仕事や働き方5選


漢方に関わる仕事は、漢方薬局や漢方クリニックに勤務する以外にも、オンライン漢方相談や健康経営の専門家など、さまざまな働き方があります。
また「漢方薬」と聞くと薬剤師をイメージする方が多いかもしれませんが、登録販売者*、管理栄養士、助産師など、さまざまな医療資格と組み合わせて働いている方もいます。



山川裕子さん
ここでは、漢方を取り入れた働き方の具体例として、実際に活動している方の事例をもとに、5つのスタイルをまとめました。詳しく見ていきましょう。
オンライン漢方相談|薬剤師×漢方
オンライン漢方相談とは、漢方に関する悩みや体質についてインターネットを通じて相談するサービスです。働き方としては、漢方薬局に所属して行う方法のほか、自分で集客してサービスを提供する方法もあります。
筆者も漢方薬剤師として、過去に個人でオンライン漢方相談を行っていました。



山川裕子さん
漢方薬の提案だけでなく体質チェックや生活上のアドバイスも行うため、健康をトータルにサポートできるやりがいを感じられました。
健康経営の専門家として活躍|登録販売者×漢方
登録販売者としてのOTC医薬品*の知識に漢方の知識を加えて、「漢方アドバイザー」として活躍する人もいます。[2]
さらに「健康経営エキスパートアドバイザー」と呼ばれる、健康経営に取り組む中小企業に向けて実践的な支援を行う専門家としての資格を活かすケースもあります。[3]



山川裕子さん
漢方の視点を取り入れた健康カウンセリングや、食事・睡眠・運動に関する指導を行うことで、毎日の健康管理に貢献できるでしょう。
薬膳の講座や料理教室を開講|管理栄養士×漢方
管理栄養士としての食の専門知識に、漢方や薬膳*の考え方を加えることで、薬膳の基礎を学べる講座や季節に合わせた薬膳料理教室などを開けます。オンラインでの開催も可能なため、活動の幅を広げやすいのが特徴です。



山川裕子さん
薬膳メニューの考案やレシピの提供は、健康志向が高まる現代において、今後ますます注目されていくでしょう。
薬膳で妊活や妊娠中、産後をサポート|助産師×漢方
妊活中から妊娠期、産後にかけては心身ともに不安定になりやすい時期です。
体質やバランスを重視する漢方や薬膳は、この時期のサポートと相性が良く、安心感を与えてくれます。



山川裕子さん
妊活中の体づくりや産後の回復ケアなど、助産師が得意とするサポートに薬膳を組み合わせることで、独自性が生まれ、女性にとってより心強いサービスとなるでしょう。
漢方茶でお客様の健康をケア|薬剤師×漢方
漢方の知識を活かして、漢方茶を販売しているケースもあります。



山川裕子さん
具体的には、来店されたお客様から体調や悩みを伺い、現在の体質に合った漢方茶をおすすめしめながら、生活上のアドバイスを行います。
自分で考案したオリジナルの漢方茶を商品化・販売することで、オンラインショップやイベント出店など、働き方の幅を広げられるでしょう。
【体験談】漢方を使った働き方のケース2選


ここでは、漢方の知識を活かしながら働いている薬剤師2人の体験談をご紹介します。



山川裕子さん
実際のエピソードや仕事に対する想いを知ることで、漢方を仕事にするとはどういうことなのか、イメージをより具体的に描けるでしょう。
ケース1|体質の根本改善に興味を持ち漢方薬局へ転職
「服薬指導だけでなく病気予防の部分でも力になりたい」と、調剤薬局から漢方薬局へと転職した高橋彩さん。
まだ相談業務は行っていないものの、「将来的には漢方相談ができるようになりたい」と勉強を続けています。
漢方では同じ症状でも体質によって処方が異なるため、深い知識が求められることを実感しているそうです。



山川裕子さん
さらにオンライン相談を個人で受ける場合には、SNS発信などを通して自身の認知度や信頼を高める努力も欠かせません。
現在は、ダブルワークを視野に入れつつSNS発信にも挑戦していきたいと考えています。
ケース2|相談&飲食のマルチ展開で薬膳Barを運営
調剤薬局を退職後、薬膳の飲食店で働き、現在は医療ライターや薬膳Barの運営者としてご活躍されているもこもこさん。派遣薬剤師やフリーランス薬剤師の仕事も掛け持ちしています。



山川裕子さん
薬膳Barでは、薬酒や薬膳茶、簡単なおつまみを提供するほか、お客様からの希望があれば中医学における体質の説明や養生法のアドバイスもしているとのこと。
「予防から治療まで、健康に対する全体的なアドバイスができる人になりたい」と話しており、漢方を活かした新しいキャリアの道を切り開いています。
漢方知識を活かして働くメリット3つ


漢方の知識を仕事に活かすことは、医療資格を持つ方にとって大きなメリットがあります。
近年は予防医療やセルフケアへの関心の高まりから、漢方への注目度も増しています。漢方に関する深い知識は、将来的にニーズが高まっていくでしょう。



山川裕子さん
ここでは、漢方を仕事にする具体的なメリットを3つご紹介します。
医療資格と組み合わせることで差別化できる
漢方は、一人ひとりの体質をしっかりと見極めたうえでアドバイスする必要があるため、専門知識がなければ対応が難しい分野です。
その中で、医療資格とあわせて漢方の知識を持つことは専門性や独自性につながり、自分ならではの大きな強みになるでしょう。
病気の予防から治療まで幅広く関われる
多くの医療職は、病気を発症してからの「治療」に関わります。一方、漢方は病気になる前の「未病」の段階からサポートできるのが特徴です。



山川裕子さん
年齢を重ねても健康に活動できるよう、日頃から小さな不調を見過ごさずケアしていくことは大切です。
漢方ではこうした健康全体に関する相談からアドバイスまで主体的に関われるため、やりがいも大きいでしょう。
ライフスタイルに合わせやすい
漢方を活かした仕事の形は、薬局やクリニックなどの医療現場に限らず、オンラインや個人活動などさまざまです。
自宅からオンライン相談をしたり、自分で日程を決めて講座を企画したりと、働き方を柔軟に選択・調整できます。



山川裕子さん
実際に筆者も出産後、在宅で時間に縛られない働き方を模索し、オンライン漢方相談を行っていました。
漢方の仕事を未経験からはじめるには


漢方の仕事に挑戦したいと思っても、未経験だと不安に感じる方もいるかもしれません。
特定の資格が必須というわけではありませんが、ある程度の専門知識は求められます。大学での漢方の授業だけでは十分でないことが多いため、新たに学び直す必要があるでしょう。



山川裕子さん
ここでは、漢方について学ぶ手段を3つに分けてご紹介します。
実務経験を積みながら学ぶ
漢方薬局や漢方クリニックで働きながら知識とスキルを習得していく方法です。
患者さんの相談を間近で聞いたり、実際にコミュニケーションをとったりしながら学べるため、実践力が身につきやすいというメリットがあります。
ただし、専門知識がほとんどない状態で働きはじめると、業務についていくのが大変に感じるかもしれません。



山川裕子さん
事前に基礎知識を学んでおくとよりスムーズでしょう。
独学で知識をつける
漢方に関する書籍やオンライン記事を活用したり、セミナーに参加したりして、自力で学ぶことも可能です。
手軽にはじめやすいものの、自分で計画立てて学習を進めなければならないため、途中で挫折してしまうリスクがあります。
また、実際に漢方を仕事にする場合は、知識だけでなくカウンセリング力も求められます。



山川裕子さん
独学ではアウトプットの機会が限られるため、実践力を養うには工夫が必要でしょう。
漢方に関する講座を受講する
漢方について学べる講座に申し込み、受講する方法もあります。
多くの講座では、漢方の基本的な概念から実践までカリキュラムに沿って体系的に学べます。さらに、同期の受講生と一緒に学べる環境であれば、カウンセリングのロールプレイングを通じて実践力を養えるのも大きなメリットです。
漢方知識をプラスして、働き方の幅を広げよう


漢方の知識を医療資格と組み合わせることで、独自の強みを持ちながら、多様な働き方を実現できます。一人ひとりの健康とじっくり向き合えるため、仕事のやりがいも大きくなるでしょう。



山川裕子さん
病気の予防やセルフケアとして漢方への関心が高まっている今、専門的な知識と実践的なスキルを身につけて、新しいキャリアの幅を広げていきましょう。
オンライン漢方相談のはじめかた講座
漢方の歴史・現状、営業形態やオンライン店舗見学、勉強方法、ロールプレイングまで実践的に習得できる講座です。医療現場での専門知識や経験と漢方知識を掛け合わせて働きたい方に特におすすめです!