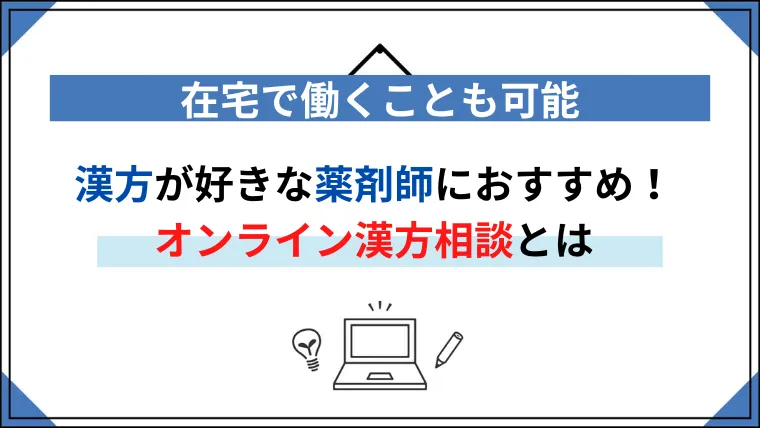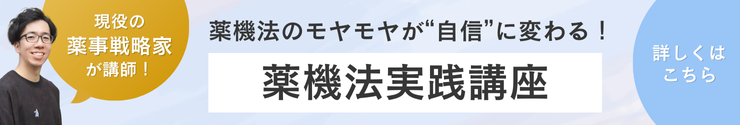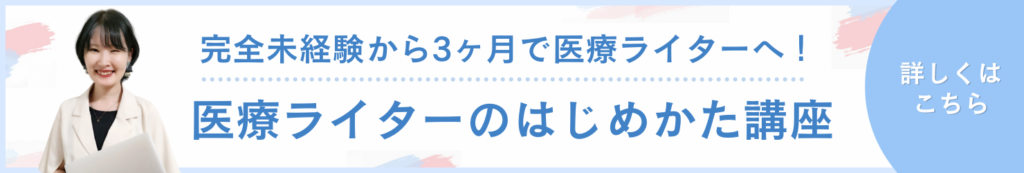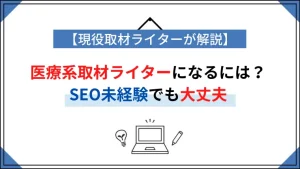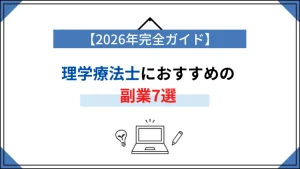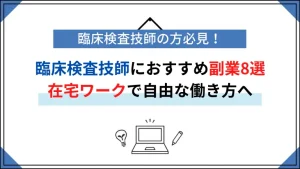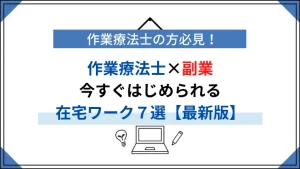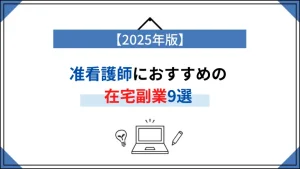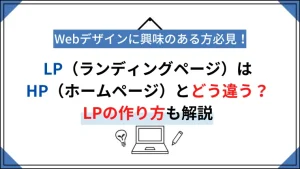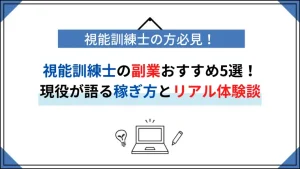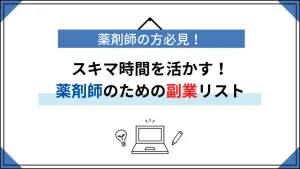医療ライターとして活動していく中で「薬機法は知っておくべき知識」と聞いて不安を感じたことはありませんか?
薬機法について聞いたことはあるものの、薬機法の知識はなぜ必要なのか、どのように勉強すれば良いのか悩む方も多いでしょう。医療ライターの中には、さらにスキルアップして、単価をあげたいと考えている方もいるかもしれません。
 薬剤師ライター
薬剤師ライターさっちゃんさん
薬機法の知識を身につけると、自分の身を守るだけでなく、クライアントから信頼される医療ライターになり、結果的に単価アップにつながりやすくなります。
この記事では、薬機法を学ぶメリットや具体的な勉強法について、現役薬機法ライターであり薬剤師でもある筆者が体験談を交えて紹介します。実際に受けた案件も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
医療ライターに薬機法の知識が必要な理由


薬機法違反を避けるために、医療ライターには薬機法の知識が必要です。
「薬機法違反」と聞くと、難しそうで不安に感じる方もいるかもしれません。
ただ、医療ライターに求められるのは薬機法の一部の知識。基本を理解し、ルールを守れば、決して怖いものではありません。



さっちゃんさん
まずは、薬機法の概要と必要な理由について説明します。
薬機法は医薬品などの販売や広告に関する法律
薬機法とは、医薬品や医療機器等の品質・有効性・安全性を確保するために作られた法律です[1]。製造や販売、広告などについて細かなルールが定められており、対象となるのは以下の5つになります。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
- 再生医療等製品



さっちゃんさん
これらに関する記事を書く際は、薬機法の規制対象となる可能性があるため、注意が必要です。
なお、健康食品やサプリは本来、薬機法の規制対象外ですが、「○○に効く」「××が治る」といった効果を明示する表現を使うと、薬機法に関わる可能性があります。
そのため、健康食品やサプリに関する記事を執筆する際も薬機法や健康増進法に関する知識が必要です。
医療ライターも賠償責任を問われる可能性がある
薬機法違反の記事を執筆するとクライアントから賠償責任を問われたり、措置命令を受ける可能性があるため注意が必要です。
逆に医療ライターが必要な薬機法の一部の知識を理解して、執筆すれば問題なく執筆活動ができます。



さっちゃんさん
もし、表現に不安がある場合は、目安として薬機法のチェックツールを活用する方法もあります。
医療ライターが薬機法を学ぶ3つのメリット
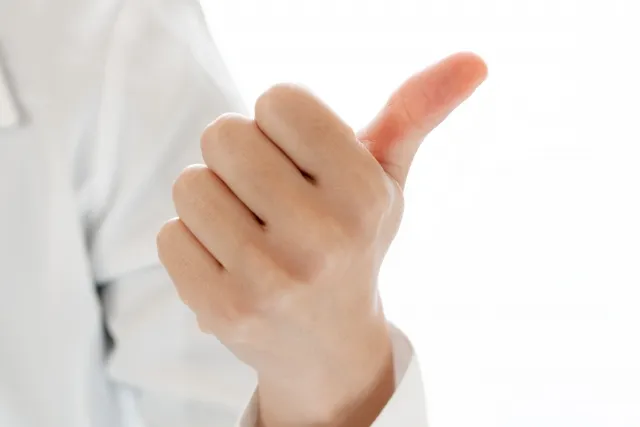
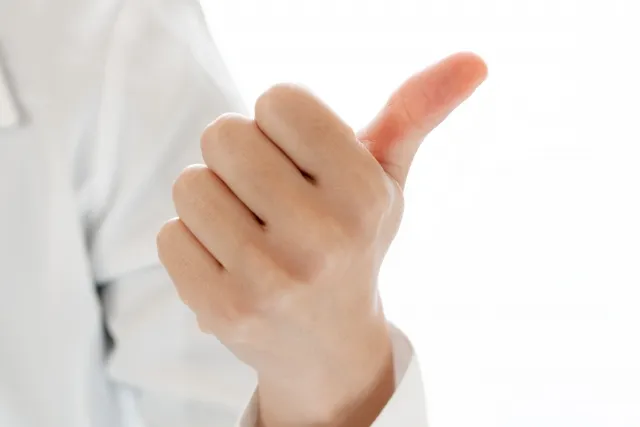
薬機法は医療ライターにとって重要な知識であり、強力な武器にもなります。ここでは、筆者が実際に薬機法を学んで感じた3つのメリットを紹介します。



さっちゃんさん
医療ライターとして、さらに活動の幅を広げたい方はぜひ参考にしてください。
1.薬機法への心理的ハードルが下がる
薬機法を学ぶことで、違反を避ける力が身に付き、不安を軽減できます。
以前は薬機法が関わる案件を不安に感じ、断るケースも少なくありませんでした。ただ、今では違反リスクを意識しながら執筆できるようになったため、不安を感じず引き受けられるようになりました。
また、中には薬機法が関わることにクライアントが気づいていない案件もあります。



さっちゃんさん
薬機法を学んだことで必要に応じて契約内容を確認するようになり、自分を守る意識が高まったのも大きな変化です。
医療ライターの案件には薬機法が関わるケースが多くありますが、正しい知識があれば必要以上に心配せず、適切な対応ができるようになります。
2.クライアントから選ばれる医療ライターになる
薬機法を理解している医療ライターは、クライアントから信頼され、重宝される存在になります。
薬機法を意識しすぎると、商品の魅力が十分に伝わらなかったり、わかりにくい記事になったりしがちです。その反面、薬機法を学んだおかげで違反のリスクを下げつつ、魅力的な表現に言い換えることも可能です。



さっちゃんさん
実際に筆者が言い換え表現を提案した際、クライアントから感謝の言葉をいただき、今でも継続的に仕事を依頼されています。
また、薬機法についてスムーズに話ができるようになり「この人は薬機法を知っているな」と信頼を得やすくなりました。記事執筆だけでなく、クライアントとのコミュニケーションにも役立っています。
このように、薬機法を学ぶとほかの医療ライターとの差別化につながり、継続的な依頼を得るきっかけにもなります。
3.高単価案件を獲得できる可能性がある
薬機法に関わる記事は、高単価な案件を獲得できる可能性があります。薬機法関連の文字単価の相場は以下の通りです。
- はじめたばかり:2~3円/文字
- 実績ができてから:3~5円/文字
- 実績が安定してから:5円~/文字



さっちゃんさん
筆者も薬機法を学んだことで、文字単価3円のSEO記事を受注できました。
高単価案件は応募者が多く競争率も高くなります。そこで、薬機法のスキルをプロフィールや応募文に記載すると、高単価案件を獲得できるチャンスが増えるようになります。実際に、応募者60人以上いる高倍率案件も受注できました。
薬機法を守ることは、交通ルールを守るようなもの。薬機法は遵守すべきものになりますが、薬機法に詳しいライターはまだ多くはないため、差別化でき高単価案件の受注にもつながりやすくなります。
【体験談】薬機法関連の案件はどんなものがある?


薬機法関連の案件は、実は多岐にわたります。医療ライターといえばSEO記事の執筆を思い浮かべる方が多いかもしれません。実はSEO記事以外にも活躍できる分野がたくさんあります。



さっちゃんさん
ここでは、筆者の体験談を交えながら、どのような案件があるのかをご紹介します。
健康食品・化粧品メーカーなどのSEO記事
健康食品や化粧品メーカーが自社商品へ誘導するためのSEO記事作成の仕事があります。
広告と聞くと、LP(ランディングページ)*やバナー広告のイメージが強いと思いますが、以下の3つの要件を満たすとSEO記事も広告として規制の対象になります[1]。
- 顧客を誘引する意図が明確であること(誘引性)
- 特定の医薬品などの商品名が明記されていること(明示性)
- 一般の人が認知できる状態であること(一般性)
規制の対象となるため、SEO記事であっても薬機法を意識した表現が求められるのです。



さっちゃんさん
筆者は主にサプリメント会社のSEO記事を中心に執筆していますが、ほかにも化粧品メーカーやクリニックのSEO記事案件もあります。
SNSへの投稿記事
InstagramやYouTubeなどのSNSに投稿する記事も、上記の3つの要件を満たせば薬機法の対象になります。
SNS分野で特に多いのは、化粧品会社やサプリメント会社から依頼されるPR案件です。インフルエンサーの方なども関わってくる案件です。



さっちゃんさん
筆者も個人のInstagramでサプリメント会社からPR案件を依頼されたことがあり、薬機法の知識が必要な案件になりました。
LPの原稿作成
薬機法に対応したLPの作成も案件のひとつです。
LPはSEO記事よりも読者に強く訴求する言葉が求められるため、商品の特徴を深く理解する必要があります。執筆前にはクライアントから商品の詳細なヒアリングが必要になるため、その分単価は高めで1件あたり数万円になります。
なお、LPのデザインは専門のデザイナーが担当するケースが多いです。クライアントや連携するデザイナーさんとのコミュニケーション力も必要になってきます。
医療ライターに薬機法の資格は必要?
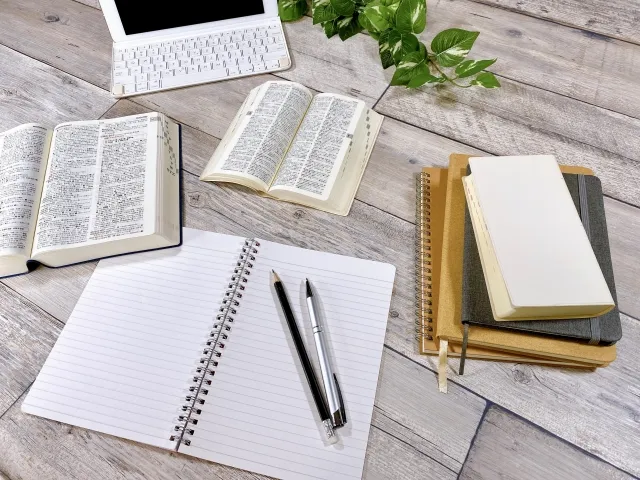
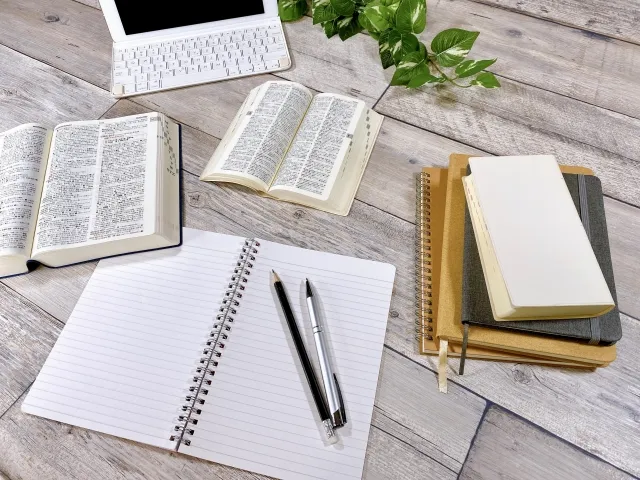
「薬機法関連の案件に挑戦したい!」と思ったとき、気になるのが資格の有無ではないでしょうか。
結論から言うと、医療ライターとして薬機法の資格は必須ではありません。



さっちゃんさん
本章では、実際に活動するうえで資格が必要かどうかを詳しく解説します。
資格よりも実践的なスキルが重視される
薬機法の案件をこなす上で大切なのは、資格よりも実践的なスキルです。
クライアントが求めているのは、SEO記事や広告記事を通じて商品の魅力を伝え、売上をのばすことです。薬機法違反を避けつつ、魅力的な表現を工夫できるスキルが求められます。



さっちゃんさん
実際に、クライアントから「もう少し魅力的な表現にしてほしい」といった要望を受けることも少なくありません。
もちろん、資格をとる過程で基礎的な知識は身につきます。ただ、実際の案件で対応できる実践力がないと、クライアントの要望に応えることが難しくなるでしょう。
資格があればクライアントからの信頼度UP
とはいえ、資格はまったく必要ないわけではありません。薬機法の資格があることで、クライアントからの信頼度が高まり、仕事の幅が広がります。
薬機法の資格があると、以下のメリットがあります。
- クライアントからの信頼度があがる
- プロフィール文や応募事にアピールできる(権威性が高まる)
- 薬機法の有資格者限定の案件にも対応できる
医療ライターとして薬機法案件に取り組む際は、実践的なスキルが最も大切です。
ただ、必須ではありませんが、資格を習得するとクライアントから信頼できるライターと判断されやすいです。



さっちゃんさん
将来的に薬機法を武器にして活動したい場合、資格習得をおすすめします。
薬機法の学び方とおすすめ書籍3選
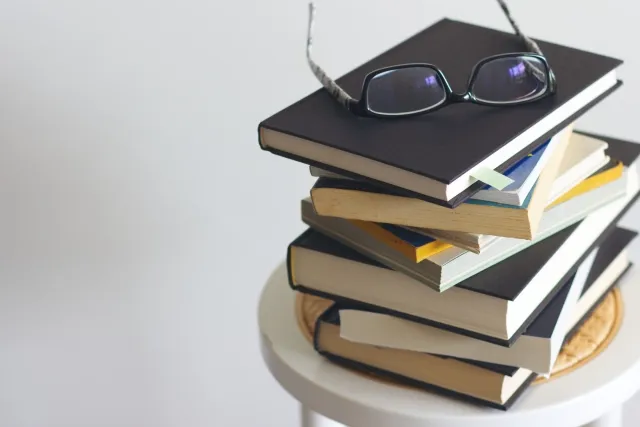
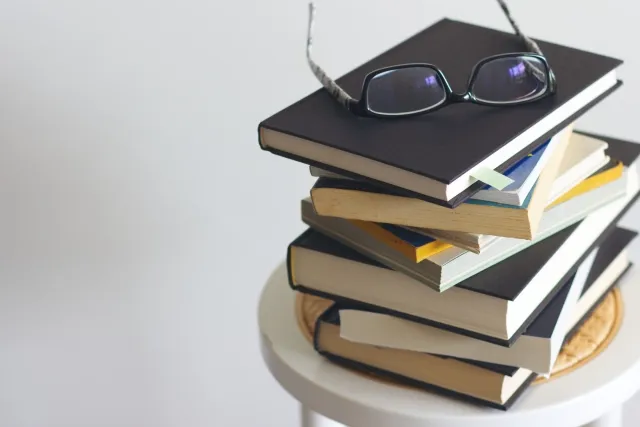
「薬機法の知識が必要なのはわかったけど、どうやって学べばいいの?」と悩む方も多いと思います。



さっちゃんさん
本章では、筆者が実際に学んだ方法を紹介するので、自分に合った方法を見つけてみてくださいね。
手軽にはじめられるおすすめ書籍も3冊ご紹介します。
実践的な講座を受ける
薬機法で最も必要な実践的スキルを身につけるなら、現役薬機法ライターが主催する講座の受講がおすすめです。
筆者は独学で医療ライターをはじめましたが、薬機法のような法律に関わる分野は独学ではリスクが高いと感じ、講座を受講しました。
すぐ仕事に活かしたかったため、実務経験豊富な現役薬機法ライターから直接学べる株式会社Medited主催の「Medi+薬機法実践力向上講座」を選びました。講座の魅力は以下の通りです。
- 現役薬機法ライターに実案件も含めて、質問を何度でもできる(※)
- 実際の案件に近い課題がだされる
※実案件の相談は講座開始前に、運営と受講生間で守秘義務等の締結を行います。必ずクライアントへ確認の上ご相談ください。



さっちゃんさん
筆者は基礎知識もない状況で受講しましたが、解説があるため問題なくすすめられ、受講終了後もすぐに薬機法案件に対応できるようになりました。
基礎知識だけでなく、即戦力となる力を身に着けたい方におすすめです。
本を読む(Kindleを活用する)
医療ライター向けの薬機法関連書籍はKindleがおすすめです。電子書籍のみで発行している書籍や、発行日が新しく最新の情報をカバーしているものが多いためです。
とくに、現役薬機法ライターや薬機法チェック担当者が経験談も含めて執筆された書籍は、実践的な内容が多く勉強になります。Medi+の講師や卒業生が執筆しているものも多く、講座を受けるか迷っている方におすすめです。



さっちゃんさん
本章では、筆者が実際に読んで役立った本をご紹介します。
改訂版!ゼロから学ぶ薬機法!玉井 智大 (著)
こちらの書籍は、これから薬機法関連の仕事をまずはじめてみるか考えてみたい方におすすめの1冊です。
- 薬機法の基本的な考え方
- NGとなる表現とその理由、言い換え表現
- 薬機法以外でも必要な知識になる景品表示法のポイント
など、基礎から実践に役立つ内容が網羅できるようになっています。講座を受けるか迷っている方は、まず気軽に書籍から読んでみるのはいかがでしょうか。
YMAAマーク薬機法・医療法適法広告取扱個人認証規格を受験する
コストをおさえつつ、薬機法の基礎を網羅し、資格を取得して権威性を高めたい方には、YMAAマーク薬機法・医療法適法広告取扱個人認証規格の受験がおすすめです。受験に合格するとYMAAマークが付与され、ライター活動でマークの使用が認められます。
不合格の場合でも特典として「薬機法」と「医療法分野」の必要な情報がコンパクトにまとまった受験マニュアルがもらえます。
このマニュアルを活用すれば、基礎知識を効率よく学びながら資格取得を目指せます。



さっちゃんさん
また、受験は無料で何度でも挑戦できるため、費用をかけずに資格取得に向けた学習を進められるのも大きなポイントです。
Web講習会を受ける
東京都医薬品医療機器等法Web講習会では、東京都主催の医薬品等広告講習会がYouTubeで無料配信されます。
毎年秋頃に開催され、この講習会は誰でも視聴可能で、薬機法の基本を学べる貴重な機会です。
さらに、最新の広告違反事例も紹介されるため、薬機法ライターとして活動する中で、知識のアップデート目的に継続的な視聴をおすすめします。
薬機法を習得し選ばれるライターになろう!


薬機法に違反すると、クライアントから責任を問われる可能性があります。そんなトラブルを避けるためにも、医療ライターに薬機法の知識は欠かせません。
ただ、薬機法の基本を身に着ければ、信頼される医療ライターとしてクライアントから選ばれるようになり、結果的に収入が上がる可能性があります。
また、薬機法に関わる案件はSEO記事だけでなく、SNS投稿の作成やLPの制作など、多岐にわたるため仕事の幅も広がるでしょう。
実際に活動していく上で、薬機法の資格があると信頼度がより高まりますが、実際の業務では資格以上に実践的なスキルが求められます。
学び方には、電子書籍やYMAA受験といった手軽な方法から実践向けの講座までさまざまな選択肢があります。



さっちゃんさん
自分にあった方法で薬機法を学び、選ばれる医療ライターを目指しましょう。
薬機法実践力向上講座 医療・美容・健康系のライター/デザイナー/SNS運用者に向けて、薬機法/景表法/健康増進法/医療広告ガイドラインなどを意識した「言い換え表現」を実践的に学ぶ講座です。知識があっても、実践が不安な方におすすめです!