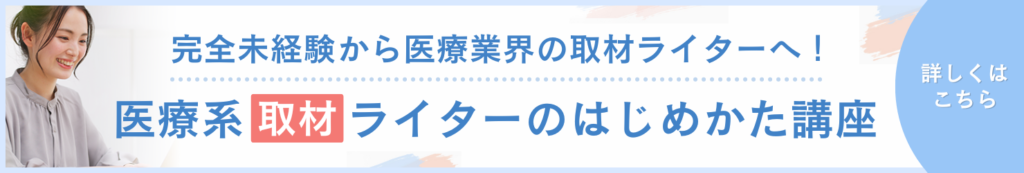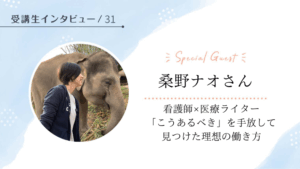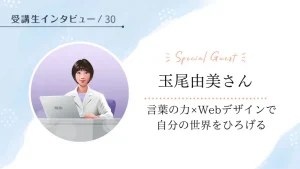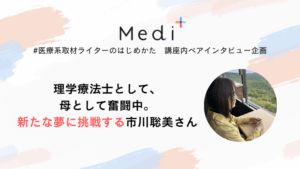Medi+
Medi+運営局
こんにちは!
「医療資格は、ずっと味方」をテーマに医療資格保有者専用の働き方の選択肢を広げるスクールプラットフォームを運営しています、Medi+です!
「Medi+医療系取材ライターのはじめかた講座」内課題のペアインタビュー&取材記事をご紹介していきます✨
今回は第5回「Medi+医療系取材ライターのはじめかた講座」を受講した星野可与さんにインタビューしました。
医療資格を取得し、キャリアを積んできたけれど、今とは違った働き方がしたいと考えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。結婚、出産など、ライフステージが変わると仕事との向き合い方が変わることもあるでしょう。
星野さんは、看護師として医療機関や学校、企業などさまざまな場所でキャリアを積んできました。現在はお子さんを育てながら医療系取材ライターを目指しています。「情報をキャッチできず、不安を抱えている方の力になりたい」と新たな挑戦をはじめた星野さん。バイタリティ溢れる星野さんのお話は、これから何かをはじめたいと思っている人の背中を押してくれます。
養護教諭、看護師の資格を持つ星野さんのキャリア


ーーさっそくですが、星野さんのこれまでの経歴を教えてください。
看護師の免許を取得後、大学で養護教諭の免許を取得しました。しかし、養護教諭としての就職の間口が狭く、最初は慢性期の病院で看護師として働いていました。臨時で募集が出ると養護教諭として働き、任期が終わるとまた看護師に戻って企業で健康づくりに関わる仕事をするという形でさまざまな仕事を経験しました。
その後は10年ほど急性期の病院で勤務。急性期の病院には怖いイメージがあり、飛び込む勇気がなかったのですが、看護師として働く中で急変にスピーディーに対応することが求められている現実を知りました。
ーーなぜ養護教諭になりたかったのでしょうか?
高校時代、保健室に具合が悪くてお世話になったというよりは、保健室の先生と話をするために同級生とよく顔を出していました。みんなが集まってくる保健室の雰囲気や、悩み事を聞いてくれる先生の姿勢に憧れて母校の養護教諭になりたいと思いました。
看護師としてキャリアアップ!2つの専門資格
ーー星野さんは看護師として、健康運動指導士と心臓リハビリテーション指導士の資格もお持ちですが、きっかけは何だったのでしょうか?
きっかけは、患者さんに運動や生活習慣について指導しているとき、具体的な方法を提案できていないと思ったからです。患者さんから「指導内容を聞いても運動の習慣がないから実際どうしたらいいかわからない」という声をいただくことが多くありました。
運動のやり方や声かけについてしっかりと勉強したいと思い、健康運動指導士*を取得しました。心臓リハビリテーション指導士*は、循環器の病院で働いていた時に、循環器の疾患を持った方にはさらに専門的な指導方法が必要だと知り、取得しました。
ーーとても勉強熱心なのですね。生活指導をする中で気をつけていたことはありますか?
病院では、看護師として患者さんに対して上の立場から話をすることが多いと感じていました。企業では患者さんというよりはお客様としてお話することになります。生活習慣や食事についてのアドバイスをする時は、なるべく視線は同じくらい、もしくはやや下から「情報提供をさせてください」というスタンスで対応するように気をつけていました。
患者さんの「求める」指導を
ーーさまざまな場所で多くの方と関わってきた星野さん。印象に残っているエピソードなどあれば教えてください。
循環器専門の病院で働いているときに、心筋梗塞が悪化し、入院した患者さんとの関わりがとても心に残っています。
退院後の生活習慣について、マニュアルどおりの指導をしたところ、患者さんは「うん、わかったよ」と口では言っていましたが、理解しているようには見えませんでした。その後も生活習慣を改善しないと再発のリスクがあるということを何度か伝えていましたが、ある日「わかってるけど、できないことを言われると脅されているように感じる」と返されてしまったんです。そのように受け取っているとは考えたことがなかったので非常に驚きました。
今までと同じ内容で指導しても効果がないと思い、具体的な方法を提示できるように関わり方を変えてみることにしました。
ーーなるほど。それで患者さんはどのように関わり方を変えたのでしょうか?
退院後の外来通院で再度お会いする機会があったので、どのようなことだったら実行できそうかを詳しく聞きました。すると、減塩の仕方がわからなくて困っていることや、息が切れて脈が上がるほどの運動は難しく感じてることを教えてくれました。
食事に関しては調味料の工夫の方法についてお伝えし、運動については心臓に病気がある人は適度に軽く汗ばむくらいの運動で問題ないこと、目標となる脈拍などの数値を伝えました。改めて具体的な方法を提案すると「自分の中でも考えて取り組める気がする」と話してくれました。
その後、生活習慣が改善され、体重や血液検査のデータが良くなりました。自分の関わりが効果的だったのだと嬉しくなりましたね。
患者さんが抱える苦悩にもっと寄り添いたい


ーー医療系取材ライターを目指したきっかけを教えてください。
新型コロナウイルスの流行と出産が重なり、仕事を辞めていましたが、もう一度何かはじめたいと思うようになりました。
ただ、これまで病院や学校、会社勤務などさまざまな職を経験してきたなかで、これから先も医療機関で看護するというイメージはつきませんでした。医療機関だと、患者さんと接する時間が短くて……。本当はもっとお話を聞いて、患者さんが抱える苦悩に向き合って看護したかったという後悔が残っていました。
こうした気持ちをつなげられるような働き方はないかと探していた時に見つけたのが「医療系取材ライター」でした。SNSやWebサイトで医療系取材ライターの方の記事を見つけたんです。さまざまな人の話を聞き、必要としている人に情報を届けられると思いました。
また、転職サイトで自分と近しい年齢やキャリアの方の体験談が掲載されているのも読み、自分もこんな記事を書きたいと思いました。読んでいると背中を押してくれるような、新しいことをはじめたいと思ってもらえるような記事を届けたいです。
取材記事の執筆は、相手と自分の気持ちがリンクして、本当に言いたかったことを表現できる楽しい作業だと思っています。これから一番楽しみだと思っている部分です。
家族のサポートで子育てと仕事を両立


ーー星野さんは、子育てもされているということで、仕事と子育ての両立は大変だと思うのですが、どのようにバランスを取られていますか?
毎日葛藤しています。子どもの負担になる疲れ方をしないよう意識しています。
出産前は仕事や勉強、自分のやりたいことすべて、疲れて動けなくなるくらいやり切っていました。しかし今は、子どもに接する時間が減ってしまったり、相手にできないほど疲れてしまったりすることがないように意識しています。
正直、時間にあまり余裕はありませんが、医療系取材ライターとして働くにあたり、子どもとの関わり方を見直し、自分のやりたいことを整理して進めていきたいと思っています。
ーー今回の講座を受けるにあたってご家族のサポートもあるのでしょうか?
はい、特に夫がパソコンの設定などで助けてくれています。私はあまり詳しくないので困った時は頼りにしています。両親も同居しているので、これからは子どもの世話をお願いしたり、朝早めに起きたりして、時間を確保していきたいです。さまざまな障害も自分一人では手に負えず途中で諦めていたかもしれません。家族に感謝ですね。
誰かの活力に!新たな挑戦


ーーこれからどのような記事を書いていきたいですか?
医療現場で医療や介護に携わるさまざまな方や通院しながら闘病している患者さんのインタビューがしたいと思っています。
また、支援グループにも興味があります。ピアカウンセリング*を運営している団体やNPO法人など、実際に現場で働く方の声を聞いて、必要としている人に知っていただくお手伝いができたらいいなと思っています。
ーー具体的にどのような人にインタビューしたいですか?
これまで一緒にお仕事してきた方や、アクティブに活動されている身近な医療従事者の方にインタビューしてみたいです。
例えば、新境地に向け情報発信や研究をしている医師がいます。こういう方々のお話は、パワフルでエネルギーをもらえるので、読者が元気にできるようなインタビュー記事を書いて、誰かの活力になればと思っています。
ーー本日はありがとうございました。
ペアインタビューをしてみて:取材ライターの感想


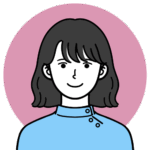
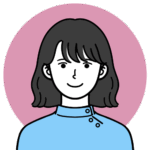
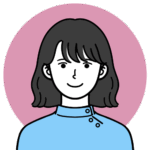
野田梨央さん
はじめてのインタビューで緊張していましたが、星野さんのエネルギー溢れるお話に元気をいただきました。
笑顔で丁寧にご自身の経験を語ってくださったので、もっと深掘りできるような質問を考えられたら良かったと反省しました。私も星野さんと同じ看護師の資格を持っていますが、患者さんへの接し方や指導に対する熱意はとても勉強になりました。今後、医療系取材ライターとして多くの人と接する上でも、活かしていきたいと思います。
インタビューする立場と受ける立場の両方を経験して、これからの活動が楽しみになりました。今回は貴重な経験をさせていただきありがとうございました。
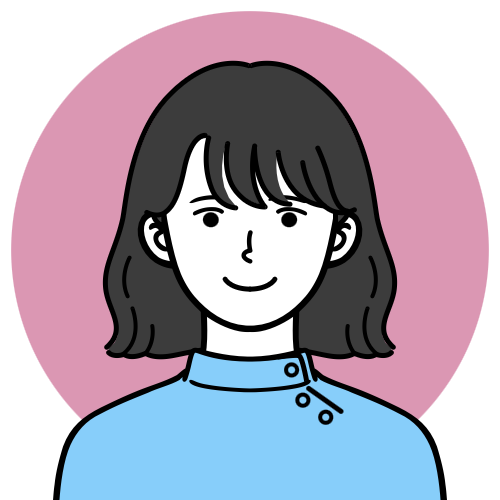
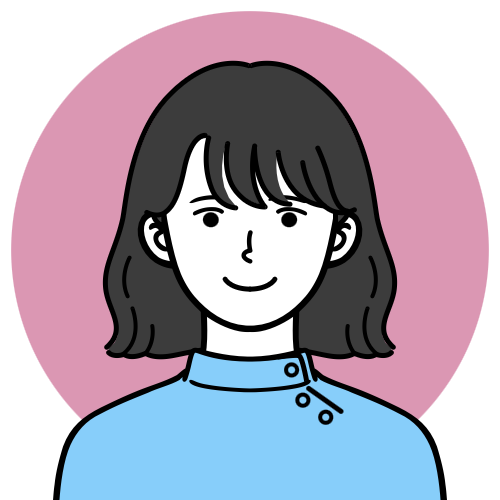
看護師取材ライター:野田梨央さん
2017年に正看護師資格を取得し、急性期病棟やクリニックに勤務。人の想いに寄り添い、情報を求めている人の助けになりたいと「Medi+医療系取材ライターのはじめ方講座」を受講。看護師経験を活かした和やかな取材とわかりやすい記事作成を心がけている。趣味は旅行、お笑い鑑賞、編み物。
野田梨央さんも受講、「Medi+医療系取材ライターのはじめかた講座」とは?